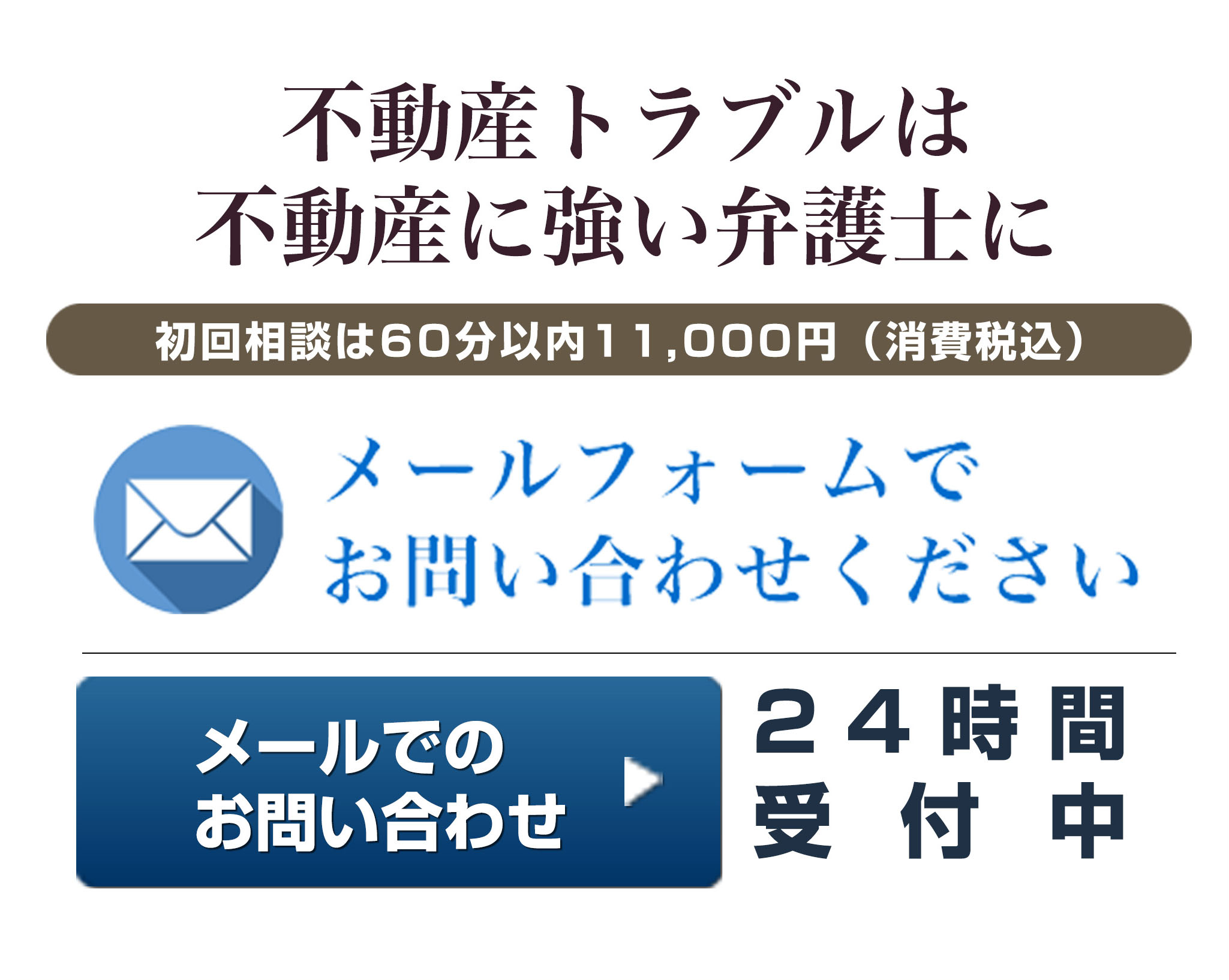賃料が長年据え置かれている場合、増額を請求できる?
建物を店舗・事務所等のテナントに貸している、又は居住用に賃貸しているが、賃料が長期間据え置かれており、周辺の賃料相場と比較してかなり低額だという場合、賃料の増額を請求できるのでしょうか。
賃料増額請求権
借地借家法32条1項は、建物の賃料が、①土地若しくは建物に対する租税その他の負担〔固定資産税・都市計画税等〕の増減により、②土地若しくは建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により不相当となったとき、③近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときには、賃貸人側から、将来に向かって〔請求時点から以前にはさかのぼらないという意味です〕賃料の増額を請求できる旨を規定しています。
ですので、賃料が長期間据え置かれているため、周辺の賃料相場は土地の価格の上昇等に伴い上昇しているのに、対象物件の賃料水準がかなり低額だという場合には、賃料の増額請求が認められる可能性があるのです。
ただし、一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、当該期間中の賃料増額請求は認められません(借地借家法32条1項ただし書き)。
また、定期借家契約で、賃料改定に関する特約がある場合には、賃料増額請求はできません(借地借家法38条9項)。
「新規賃料」と「継続賃料」の違い
《現時点で建物賃貸借契約を結ぶ場合、賃料はいくらが相当か》という《新規賃料》の問題と、《当事者の合意による現行の賃料額が、その後の事情の変更により不相当になっているか》という《継続賃料》の問題とは異なります。
賃料増額請求においては、《継続賃料》が問題となるのであって、周辺の賃料相場より低いからといって、いきなり《新規賃料》の水準まで一気に増額するのは困難です。
既に賃貸借契約がありますので、従前の合意を無視することはできず、従前合意した現行賃料の水準を踏まえつつも、それが経済事情の変化等によって不相当になっている、という主張をすることになります。
直近合意時点の重要性
契約当事者が現行賃料を合意し、適用した時点のことを「直近合意時点」といいます。賃料増額請求は、直近合意時点における合意を見直すものであり、直近合意時点が経済情勢の変動や、その他の諸般の事情の変化を考慮する起点となります。そのため、直近合意時点がいつであるかが重要です。
直近合意時点については、判例上、契約当事者が現行賃料について「現実の合意」をした時点と考えられています(最二小判平成20年2月29日)。
賃料を据え置きとして合意更新した場合、実質的な賃料交渉を経た「現実の合意」がなく、機械的に合意更新したに過ぎない場合には、直近合意時点にならないと解されています。
直近合意時点がいつかについては、当事者間で良く争われる論点です。
地価上昇局面では、直近合意時点を後にずらされることを避けるため、安易に合意更新をしないで自動更新又は法定更新にしておいた方が良いケースもあります。
直近合意時点に争いがある場合、後述の裁判鑑定について、直近合意時点がAの場合、Bの場合と場合分けをして鑑定を依頼することもあります。
継続賃料の鑑定手法
賃料増額請求については、不動産鑑定士が関与することが多く、不動産鑑定士は、一般に、「差額配分法」、「利回り法」、「スライド法」という手法を用いて《継続賃料》を鑑定することになります。
このうち「差額配分法」の考え方は、新規賃料水準と現行賃料水準との乖離(賃料差額)のうち、賃貸人等に帰属する部分を判定して、これを現行賃料水準に加算するという考え方です。賃料差額の発生について、賃貸人、賃借人のどちらにも帰責性がなく、経済事情の変動により賃料差額が発生しているという場合には、「1/2法」といって、賃料差額の1/2相当を現行賃料水準に加算して継続賃料を決める方法が多く使われます。
ですので、大雑把に言うと、新規賃料水準と現行賃料水準を折半した水準まで現行賃料を引き上げるという考え方になります。
この考え方は、直近合意時点における賃料が当該時点においても低額であり、市場賃料との間に乖離があった場合に、その乖離を、賃貸人・賃借人双方の利害に配慮しつつ、一定程度埋めていくという考え方です。
「利回り法」の考え方は、直近合意時点(現行契約当事者が現行賃料を現実に合意し、適用した時点)における、基礎価格に占める純賃料の割合(直近合意利回り)を踏まえ、一定の修正をした上で、「継続賃料利回り」を求め、基礎価格に継続賃料利回りを乗じ、さらに必要諸経費等(固定資産税・都市計画税等)を加算して賃料を求める考え方です。
この考え方は、直近合意時点において当事者の合意した利回りを重視する考え方です。利回りが同じでも、土地建物の価格が直近合意時点以降に上昇していれば、それに伴って賃料は上昇することになります。
「スライド法」の考え方は、直近合意時点における純賃料(実質賃料-必要諸経費等)に、「変動率」を乗じ、必要諸経費等を加算して賃料を求める考え方です。
「変動率」は、直近合意時点から賃料改定時点までの経済情勢等の変化に即応する変動分を表すものであり、土地・建物価格の変動、路線価の変動、固定資産税の変動、物価変動等を表す各種指数を総合して求めます。
この考え方は、マクロ的な経済情勢の変化を良く反映させる点に特徴があり、直近合意時点における合意を尊重しつつ、合意の前提となった経済情勢等に変動があったことを反映させる考え方です。
不動産鑑定士はこれらの手法を、事案に応じた適切な割合で総合して結論を出すことになります。なお、近時は、直近合意時点以降の経済事情の変動に注目する「スライド法」を重視する考え方が強くなってきています。
おおざっぱに言いますと、例えば東京23区内の商業地で、賃料が5~6年以上据え置かれている一方で、周辺の土地の価格がその間に3割以上上昇しているといったケースでは、土地価格の上昇に連れて周辺の新規賃料相場も上昇していることが多く、ある程度コストと時間をかけても賃料増額を求めるメリットがあることが多いといえます。
ここ数年、都内の地価が上昇しており、店舗・事務所や賃貸マンションについて、賃料増額請求を行う賃貸人の方が目立って増えています。
賃料増額請求権の行使方法
賃料増額請求権は「形成権」と解されており、意思表示によって効力を生じますが、いつ増額請求の意思表示があったのか、いつから賃料増額を求めるのかを明確にするため、内容証明郵便等の文書によって行うことが必要です。
なお、増額を求める金額については必ずしも明記する必要はなく、「相当額」への増額を求めるという形でも賃料増額請求権を行使可能です。
一度増額請求の意思表示をすると、いわば紛争状態に突入しますので、安易に行うことは避け、事前に弁護士に相談することをお勧め致します。
多くのケースでは、具体的な増額後の金額を提示する前に、不動産鑑定士の私的鑑定を取ることが有効といえます。
賃料増額請求後の解決方法-協議
賃料増額請求を行い、賃借人が応じてくれれば、賃料増額についての覚書等を取り交わし、賃料増額が実現します。
しかし、賃借人側が賃料増額に応じてくれない場合には、法的手続を取ることが必要となります。
なお、賃料増額請求を受けた賃借人側としては、賃料増額に応じない場合、賃料増額を認める裁判が確定するまでは、「相当と認める額」の賃料〔通常は、従前の賃料額〕を支払い続けることが可能であり、賃貸人は、増額後の賃料不払いを理由に建物の賃貸借契約を解除することはできません。また、更新時に賃料で折り合わず、合意更新しなかった場合にも、定期借家契約でなく普通借家契約の場合には、自動更新又は法定更新により、契約自体は更新されることがほとんどです。
もっとも、最終的に賃料増額を認める裁判が確定した場合には、賃料増額請求の時点にさかのぼって増額分の支払を請求できます。また、増額後の賃料と支払済みの賃料との差額(不足額)に年10%の利息を付けて支払うよう賃借人に請求することができるという規定もあります(借地借家法32条2項)。
賃料増額請求後の解決方法-調停
賃料増額については、原則として、いきなり裁判を起こすことはできず、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義/民事調停法24条の2/もっとも、例外もあります)。
賃料増額調停は、紛争の目的である建物の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てるのが原則です。賃貸借契約書に合意管轄条項があるか、相手方と管轄合意書を結べる場合には、合意で定める当事者の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てることもできます。
東京簡裁では、賃料増額調停については、弁護士と不動産鑑定士各1名が調停委員に選任され、調停手続きを進めることが多い取扱いです。
調停手続きはあくまで話合いの手続と位置づけられており、裁判所が適切な賃料を判断して示すといったことは基本的にはしてくれません。
賃料増額請求後の解決方法-訴訟
調停でも賃料増額請求が決着しない場合には、裁判所に賃料増額請求の裁判を提起する必要があります(例外的に、調停を経ないで訴訟を提起することもあります)。
裁判では、事情の変更により従前の賃料額が不相当に低額になったといえるか、その基礎付け事実(固定資産税等の上昇、地価の上昇、周辺の新規賃料相場の上昇等)の存否や、相当といえる継続賃料の金額をめぐって、審理が行われます。
賃貸人側は、基本的に、裁判の段階までに、不動産鑑定士に依頼して、継続賃料についての鑑定評価書を提出し(私的鑑定)、適切な継続賃料の額について主張することが多いです。交渉段階から私的鑑定を取っておくことも多いです。
私的鑑定だけではなかなか裁判所がそのまま採用することは少ないため、多くのケースでは、賃貸人から、もしくは双方から裁判所に申し出て、不動産鑑定士を鑑定人に選任してもらい、継続賃料の鑑定(裁判鑑定)をしてもらうことが多いです。この場合、鑑定を申し出る当事者の側で、鑑定費用を予納することが必要です(最終的には判決か和解で鑑定費用の負担を決めますので、双方が一定の割合で負担することが多いです)。
どうせ裁判鑑定をするのなら私的鑑定は不要ではと思われるかもしれませんが、私的鑑定は、当事者の主張立証の裏付けとなるものであり、裁判所の鑑定人も私的鑑定の内容を良く検討した上で判断をしますので、私的鑑定にも十分意味があります。むしろ、賃料増額請求を行う上では、早い段階で私的鑑定は必須といえます。
裁判鑑定の結果が出ると、裁判鑑定の結果や裁判官の心証を踏まえた裁判所での和解協議により、賃料増額請求について裁判所での和解が成立するケースも多くあります。
和解ができなければ、判決となります。判決においては、通常、裁判鑑定の結果が重視されます。
賃料増額請求を弁護士に依頼するメリット
以上に見たように、賃料増額を実現するには、賃料増額請求→協議→調停→訴訟と法的手続を取っていく必要があります。
協議で解決すればコスト的には良いですが、相手次第の話であり、最終的には訴訟まで見据えて慎重に行う必要がありますので、弁護士に依頼して進めることが望ましいでしょう。
弁護士は、不動産鑑定士と連携しつつ、賃料増額の手続きを進めることになります。
弁護士に依頼することで、賃借人と直接やり取りすることなく、精神的ストレスを軽減しつつ、冷静で客観的・合理的な交渉を進めることも可能になります。
賃料増額請求をお考えの際は、不動産に強い弁護士にご相談ください。
弁護士秋山直人は、不動産鑑定士の資格も保有しており、賃料増額請求については得意分野で、力を入れています。
不動産鑑定士と連携して、多くの案件で賃料増額請求を進めており、都内を中心に、店舗・事務所・賃貸マンション等で、賃料増額を実現している実績があります。特に、コンビニ・スーパー・外食産業などの店舗や事務所用途のテナントにまとまった金額の賃料で賃貸しているケースでは、コストを考慮しても賃料増額請求を行った方が良いケースが多くなってきています。
賃料増額請求の弁護士費用
弁護士秋山直人は、賃料増額請求に力を入れており、次のような費用で事件を受任することが多い状況です。具体的には、ケースに応じて、個別に御見積りをお示しします。
〔月額報酬〕
月55,000円(消費税込)前後
*テナント1社あたり。
*交渉→調停→訴訟を通じて同一。
〔成果報酬〕
「賃料増額分の3年分」を経済的利益として、①交渉段階で賃料増額を実現した場合には、経済的利益の11%(消費税込)、②調停・訴訟段階で賃料増額を実現した場合には、経済的利益の16.5%(消費税込)
*弁護士会の基準(法律相談センター経由で登録弁護士が受任した案件の報酬基準)では「賃料増額分の7年分」を経済的利益としていますが、大幅にディスカウントしています。
*賃借人の退去を実現した場合の報酬金も設定することがあります。
〔実費支出用預り金〕
実費は月額報酬と別途に預り金から支出します。
〔鑑定費用〕
以上の弁護士費用と別に、私的鑑定費用、裁判鑑定費用の支出を見込む必要があります。
私的鑑定費用については依頼者負担となります。不動産鑑定士に依頼しますが、正式な不動産鑑定評価書を依頼する場合と、費用節約のため「価格等調査報告書」を依頼する場合があります。
裁判鑑定費用については、私的鑑定費用よりも通常高いですが、和解又は判決において、一部は賃借人の負担となることが多いといえます。