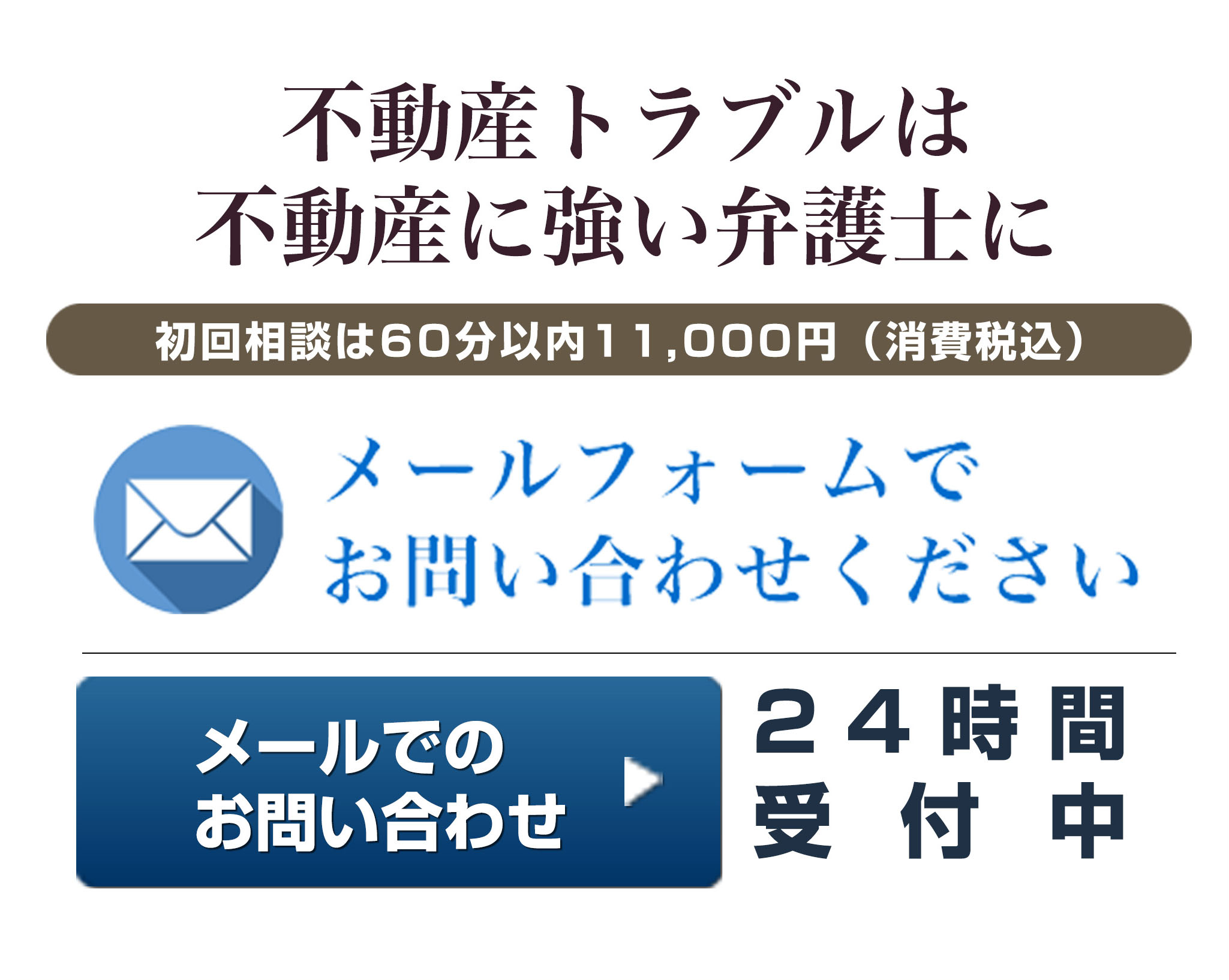漏水事故トラブルの難しさ
漏水事故
漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。
その原因を考えてみました。
1 関係当事者が多数・複雑
例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。
2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要
漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
例えば分譲マンションの場合、共用部分の配管の破損であれば管理組合が、専有部分の配管の破損であれば区分所有者が、お風呂の水の出しっぱなしといった場合には居住者が責任を負うことになります。また、リフォーム工事業者の施工ミスや、引越業者の洗濯機設置ミスといったケースもあります。漏水原因を究明するには専門業者の調査が必要になるケースがかなりあり、専門業者が調査してもなかなか原因が判明しないこともあります。原因が明確にならなければ、責任の押し付け合いが起こります。
3 保険に対する関係者の理解不足
漏水事故では、賠償責任保険の保険会社や、火災保険の保険会社が関与する場合が多いですが、特に賠償責任保険について、その性質(加害者が負担する法律上の損害賠償責任を填補する)を理解していない関係者が多いと感じます。
4 保険会社の問題点
例えば賃貸マンションの漏水事故で、建物所有者が保険に入っていなかったりすると悲惨ですが、入っているケースでも、保険会社の対応が悪いと感じるケースは多いです。
原因の一つとして、いわゆる「示談代行」が付いていないケースが多いこともあると思います。交通事故の場合、ほとんど示談代行が付いているので、被害者代理人の弁護士が保険会社の担当者と直接交渉をして交渉で解決できることも多いですが、漏水事故の場合、保険会社は交渉の矢面には出てこず、ただ見積書の査定結果だけを出して、あとは被害者側が査定結果を呑むかどうか、という交渉の余地の小さい対応をするケースが多いと感じます。(なかには減価償却率などで譲歩するケースもありますが)
また、一般的な傾向としては、保険会社の修繕工事費用等に対する査定が渋く、水濡れした財物の被害などについても対応が渋いという大きな問題があります。
修繕工事費用の見積りに対して、被害者からしてみれば「そんな金額では工事ができない」という大幅な減額査定をしてくるケースが多くあります。単価が高いとか人工が多すぎるとか、経年劣化しているから減価償却すべきだといった主張が多いですが、被害者からしてみれば、好きでこのタイミングで修繕工事をするわけではないのに、減価償却という理屈で大幅な減額をされたのでは、たまったものではありません。
この点については、裁判に至った場合の解決水準が必ずしも高くないという大きな問題が背景にあります。
5 被害者側の問題点
漏水事故は、一般的にいって、被害者側には落ち度がないケースがほとんどであり、そのために、いわゆる被害者意識が大きく、「なんで何の落ち度もないのに解決のためにこんな負担を強いられるのか」という思いが被害者に強すぎて、かえって解決が遠のいてしまうケースがあります。
責任追及すべき矛先が、本来の漏水原因者ではなく、管理会社などに向かっているケースも見られます。
こじれて長期化してしまっているケースもかなりあり、もっと早い段階で弁護士が入って交通整理をすればここまでこじれなかったのに・・・という印象を持つケースもあります。
例えば日本の裁判では、被害者の負担する弁護士費用についても、その多くは被害者の自己負担になります。この点一つを取っても、被害者にとっては納得のいかないところです。
このように漏水問題は複雑で困難なケースも多いわけですが、被害者の方も、弁護士に相談の上で、置かれた状況・現実を直視し、訴訟を起こすなら起こす、妥協するなら妥協する等と、適切に判断していく必要があると思います。
その他のコラム
不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!
お知らせ
居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故